エピソード
トリビア
1984年にアーケードで登場し、1985年7月11日にファミリーコンピュータ版として発売された『ロードファイター』は、スピードと緊張感だけで勝負するシンプルなレースアクションとして知られている。プレイヤーはシボレー・コルベットを操作し、ニューヨークからサンフランシスコまでの長距離コースを、敵車や障害物を避けながらゴールまで走り抜けることが目的であり、順位やタイムを競うのではなく、限られた燃料をどう使い切るかという生存型の設計が特徴だった。
燃料は走行中に現れる補給車に接触することで回復する仕組みで、ただ避けるだけでなく「補給を狙う」行動を組み込んだ点が、当時としては非常にユニークだった。補給を逃すとゴール前でエンストしてしまうため、スピードを保ちながら正確にぶつけるという、単純操作の中にも高度な判断が求められた。クラッシュを繰り返せば燃料は減り続け、敵車との接触やオイル、落石、工事中などの障害物もすべて致命的なリスクとして作用する。ファミコン版では全4コース構成で、各ステージの最後に残った燃料量に応じてボーナスが加算される仕様となっていた。
この作品の特徴のひとつは、ゲーム中にBGMが存在しないことだった。コース上ではエンジン音、ミサイルのような爆発音、警告音など、最低限の効果音のみで構成されており、音楽のない空間がかえってプレイヤーの集中を研ぎ澄ませた。無音の中でアクセル音が響き、燃料が残り10を切ると鳴る警告音が緊張を高める——そのストイックな設計は、家庭用ゲームの枠を超えて「純粋な操作感」を追求した結果だったといえる。
さらに、一定時間クラッシュせずに走り続けると「コナミマン」が道路脇から出現し、上空へ飛び去っていくというイースターエッグも存在した。コナミマンが登場すると、3,000点のボーナスが入る。この演出は、コナミキャラクターが自社作品に登場する最初期の例とされ、のちに『ツインビー』や『がんばれゴエモン』などでおなじみになる“自社クロスオーバー文化”の萌芽ともいえる存在だった。
当時の雑誌では「反射神経と集中力のゲーム」と評され、ゲームセンターのようなスピード感を家庭でも再現できる点が高く評価された。燃料を補給しながら慎重に走るプレイヤーもいれば、あえてノーブレーキで突き進む者もおり、プレイスタイルの違いが性格そのものを映すようだと言われたこともあった。特に子どもたちは、コントローラーを強く握り、クラッシュのたびに顔をしかめながらも再挑戦を繰り返した。音楽がなくても飽きないのは、スピードと危険が紙一重に並走していたからで、ほんの一瞬の判断が生死を分ける緊迫感こそが、『ロードファイター』の醍醐味だった。
ファミコン版はその後も長く親しまれ、1990年代には『コナミ80’sアーケードギャラリー』などに収録されて再評価された。画面下から飛び出すコナミマンの存在は今もファンの記憶に残り、単なるレースではなく「生き残りを競う」レースゲームとして、初期コナミの創造性と挑戦心を象徴する一本となっている。
NAO:総評
エンジン音しか響かないのに、これほど熱くなれるゲームがあるとはな。BGMも台詞もないのに、燃料メーターの減り具合だけで心臓がドキドキする。補給車にうまくぶつかれば安堵、逃せば絶望。単純なのに、まるで人生みたいだと思ったぜ。しかもコナミマンが出てくる演出まであるんだ。あの一瞬のご褒美が、何度も再挑戦させる。速度も判断も命懸け。ノーブレーキで走るほど、現実を忘れられた。音のない道で心だけが叫んでたんだよな。
出典:NAONATSU:総評
静かな道路の向こうで、エンジン音だけが響いてた。音楽もなくて少し寂しいけれど、その分、風を切る感じが妙にリアルだったのよ。燃料を拾えたときの安心、ぶつかったときの焦り、その繰り返しが楽しくて、気づけば何度も走ってた。コナミマンが飛んでいった瞬間は、まるで誰かが応援してくれたみたいで嬉しかったな。ゴールしたあと、手のひらがじんわり熱くて、扇風機の風が気持ちよかった。あの夏の午後を今も鮮明に覚えてる。
出典:NATSU
📘 説明書資料(ロードファイター [RC801])

説明書:レトロゲームの説明書保管庫(ロードファイター [RC801])
※Road Fighter [RC801](Famicom)(JP)
区分:説明書/Manual/Instruction_Booklet
※レトロゲームの説明書保管庫様による保存資料です。権利は各社に帰属します。
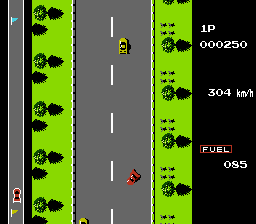


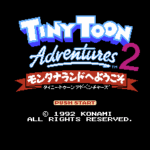
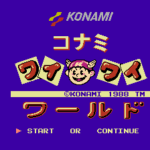

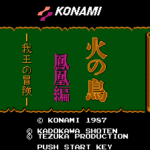



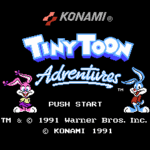


発売日:1985年7月11日|価格:4500円|メーカー:コナミ
NAO: ノーブレーキで激突上等。そんな潔いレースゲー他にない。
NATSU: コナミマンに出会えると妙にうれしくなる。